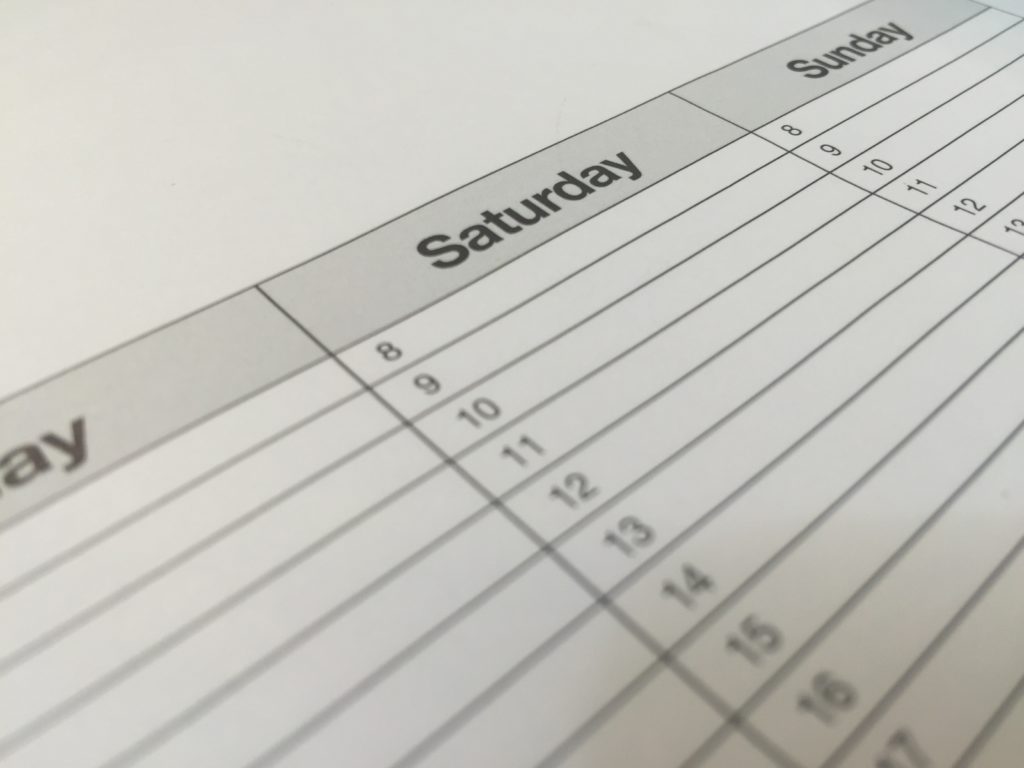
こんにちは、「学ぶことは真似ることから」まねこです。
今回は、中学生の定期テストに向けて、いつから勉強すれば良いのか、についてです。
やりたいこともあるし、部活も忙しいし、友達とも遊びたい、家ではついだらだらしてしまう(-_-;)
でも、最低限、学校の定期テスト(定期考査)では失敗したくはありません。
【中学生】定期テストの勉強はいつから始める?【失敗しないために】
そもそも学ぶ姿勢は、常日頃から持つべきで、「いつから勉強始めるの?」という問いに「毎日勉強するのが当然でしょ!」と即答されそうです。
ここでは、「最低限いついつから勉強を始めれば大失敗はしないよね」ということに絞って話をします。結論から言うと、
約3週間前、つまりテストの約21日前ということになります。
なぜ3週間前なのでしょうか。

定期テスト3週間前から勉強を始める理由
学校の定期テストに向けて勉強する教材は、主に教科書と学校ワークです。(他にもプリントやノート、資料集などありますが、ここでは省略します)
学校ワークは教科書で身につけるべきことが集約され、問題形式になっているため、勉強しやすい教材です。大いに活用しましょう!
当然個人差はありますが、学校ワークの内容を習得するには最低3週間は必要なのです。
具体的に3週間(21日間)で定期テストを失敗しない勉強の目安を見てきます。
前提条件として、テスト3週間前から必ず40分は継続して勉強します。絶対継続です。
毎日30分で学校ワーク8ページ分を解く目標です。つまり1ページ5分です。短いと思うかもしれませんが、集中すると意外と早く解けます。
最初は分からないことが多くあるため、悩み過ぎずに、わからない所は丸つけ後、教科書を調べることがいいです。時間をかけ過ぎない!
※学校の授業は超集中! 学校の授業をどれだけ集中しているかで、 学校ワークの進み具合も変わります。 学校の授業内容はその場で理解すれば、 テスト勉強もサクサク進みますよ(・ω・)ノ
1回の定期テストの勉強量を考えると、5教科合計で学校ワーク約80ページほどになります。1教科15ページほどの分量です(雑な計算ですいませんm(_ _)m)。
年間テスト回数は4~5回が大半ですので、約80ページはそこまで”ずれ”はないはずです。
毎日40分、8ページ勉強を続けると約10日間で終了します。これで終わりでありません。
残りの日数で、テスト範囲が確定しますので、やり残したところを勉強する。そして何より重要なのが繰り返すことです。
残りの11日間で、学校ワークを2回転・3回転をやり切れば、内容も頭に入ります。ちなみに2回目・3回目は一度勉強したことなので1回目より時間はかかりません。
1日40分を続ければ絶対に学校ワークを繰り返すことができ、最低限のことは身につき、テストで大失敗することはないでしょう。
ここで「毎日8ページ?きつい...(+_+)」と感じる人もいると思います。
2~3週間前は部活が停止期間になっていないことが多く、毎日40分の勉強時間の確保が難しい場合もあります。

勉強時間を確保すべきは”学校”
中学生が平日の活動時間で最も過ごす場所は”学校”です。
学校こそ、定期テストの勉強時間をつくることができます。
- 朝の登校直後のわずかな時間で学校ワークの解き直しをしておく
- 数分の休み時間で学校ワークを1ページ解く
- 数分の休み時間で学校ワークを丸つけする
- 先生の都合で、授業が急遽自習となった時間で猛然と解きまくる
- 授業の問題を解く時間に人より早く解き、教科書を読んでおく
- 部活の前の空いた時間で単語の勉強をしておく
- 友達とおしゃべりの時間を無くして勉強する
- 体育の着替えの時間を素早くして勉強する
テスト3週間前であれば、最低限40分間の勉強時間は確保したいところです。しかし、勉強出来なかった次の日は、その分学校内で時間の使い方工夫する。上記のようにいくらでも工夫できるはずです。
※勉強時間にとらわれ過ぎずに 勉強時間よりも学校ワークを解いたページに 焦点を置いた方がいいです。 40分経過したからといって、 勉強できたとは限りませんので。
さらに定期テストの得点を高め100点を目指すに何を勉強すれば良いのでしょうか。

”学校ワーク”は最低限、さらに何を勉強すべきか?
定期テストに向けた勉強は、学校ワークが有効です。しかし、これだけでは100点が取れない場合がほとんどです。
学校の教科書には問題が付属されています。当然全て解き切ってテストに挑みましょう。
教科書の所々にある”問”や”練習問題”、”章末問題”などは当然です。端にある”コラム”のような箇所も見逃してはいけません。作問者は、よく教科書を勉強し理解しているか、生徒を試します。
専用のノートが配られる中学校もあります。しかし、基本は自分が用意し板書を書いたり、配布されたプリントを張り付けたりしたものです。
ノートは黒板を写すものだけではありません。先生が言ったこともメモを取りましょう。メモするところは、強調と繰り返しです。何度も先生が伝えたこと、強調したことは当然メモ。テスト前に振り返りましょう。
プリントをつづる専用のファイルが配られる中学校もあります。
各教科で配られるプリントもワーク同様、繰り返し解くべきです。学校のワークを配布しない教科は、プリントを軸に反復練習していくといいですね。
また、毎日小テストを行う授業では、日々の小テストから出されることもしばしば。授業で先生がルーティンとしていることも解き直してテストに望めば万全です。
細かいことが出題されることもあります。狙われるのは資料集などですが、QRコードなどを利用して閲覧できることから出題する先生もいます。テスト数日前にはチェックしたいです。
予告・連絡なしに、前回の定期テストから出題されることもよくあります。
前回の定期テストで正答率が悪かったところを再度出す。期末、学年末によくある傾向です。
必ず解き直しておくべきですね。
各都道府県の過去の高校入試から出題されることもあります。熱心な中学の先生は、応用問題として定期テストに組み込む場合もあります。
中学3年生は過去問題集を購入して対策すれば、入試の準備にもなります。
しかし中学1・2年生はなかなか難しいですね。日頃から高度な学びを経験していないと対応しきれません。
では、今回は以上になります。
中学生にとって、力をつけ、試すための定期テストは重要です。何といっても高校入試の内申点に関わるビックイベントです。3週間前に勉強を始める人も、毎日コツコツ勉強している人にはかないません。日頃から継続して勉強したいものです。それでは(^^)/
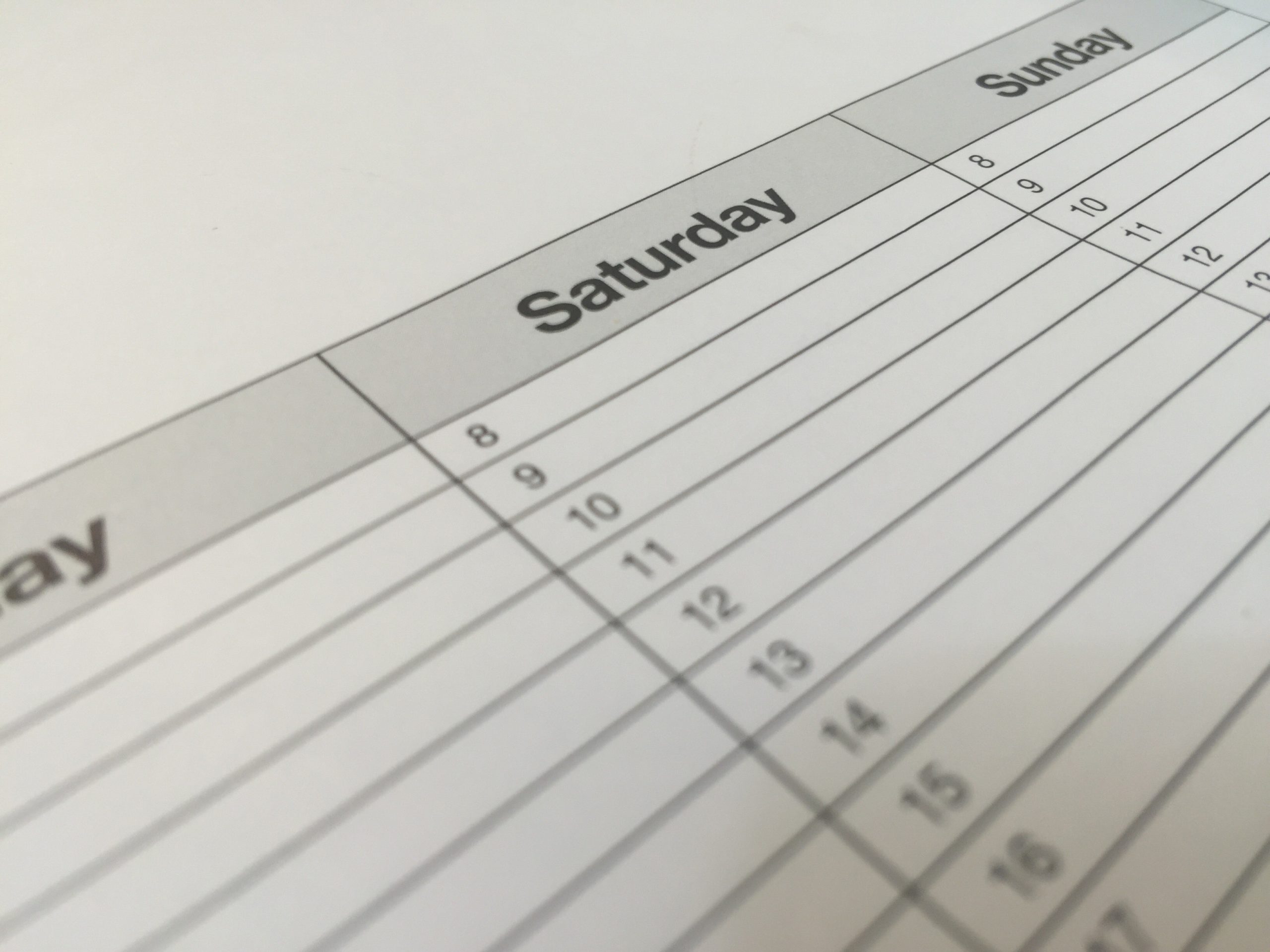








コメント