
こんにちは、「学ぶことは真似ることから」まねこです。
今回は内申点の高い中学生の特徴を紹介します。
「高校受験は、入試のテストの点数が高ければ合格できる。内申点なんか入試当日のテストで逆転できる」
確かに入試で高い得点をとれば、合格の可能性は高まります。しかし、入試は何があるか分かりません。体調が万全でないかもしれません。苦手な単元が多く出るかもしれません。
内申点が高いと高校入試が有利であることに変わりはないのです。
【中学生】「えっこんなことが!?」内申点が高い人の8つの特徴
「内申点は先生の気分次第で評価が変わる。」「先生に贔屓目に見られている奴が内申が高い。」など、内申点に対してネガティブに感じている人もいるのではないでしょうか。
正直、高校に行きたいと考えている人は、内申がある人が圧倒的に有利です。
四の五の言わず内申はとっておくべき!わざわざ先生に嫌われる行動をしないないで!
中学生は年齢的にも大人に対して何かと考える時期です。不平不満はあるでしょうが、「イラっ」としたときこそ、入試制度を思い浮かべて冷静でいてほしいです(^_-)
内申点は「提出物の見栄え、人の外見・言動・性格では評価はされない。」
ただ...実際は影響している。
内申点の付け方の基準は定められています。しかし、内申点は人が決めるものですので、恣意的とは言えないものの、多少なりとも先生の意向が影響するものです。
ここから、内申が高くなる人の特徴を紹介しますので、良ければ参考にしてください。
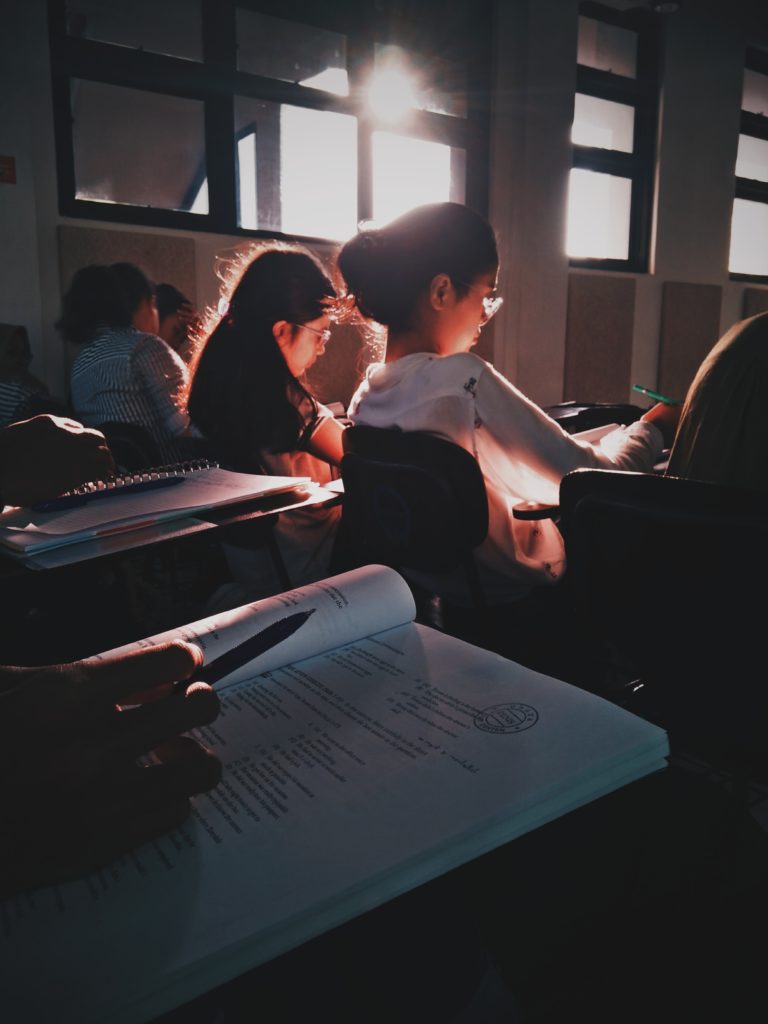
1.字が丁寧
提出物は明確に内申点として計算されます。
例えばノート。提出したかどうか、授業内容が書かれているか、最低限のルール通りに書かれているか、工夫されているか、自分の言葉で”気づき”がメモしてあるか、などをチェックされます。
内容をチェックするうえで、ノートの中身を読む必要があります。そこで、読みにくい字であれば先生はどう思うでしょうか。
たとえ、子供が書いたものであっても、何十人ものノートを見るわけですので、読み取るのが大変になります。評価は高くはならないでしょう。
一方、字が丁寧であれば、自然と読みやすくノートチェックという仕事もスムーズに進み、好感を持たれます。
字の丁寧さが全てではない。しかし丁寧に越したことはない。
美しく字より、読みやすく丁寧な字で書く。
美しく字は、簡単には身につけられません。”美しさ”の基準は人それぞれです。
心がけるべきは、丁寧に書くことです。ノートだけなく、学校のワークやプリントなどの提出物、テストの答案に書く文字も。
丁寧に書くだけで、好感を得られる可能性がありますで、すぐに意識してみてはどうでしょうか(・ω・)ノ
2.物静か
性格で評価はされません。しかし物静かである生徒の方が内申が高い傾向があります。
理由は、積極的に発言する子供は、先生の説明を遮ってしまうことがよくあるからです。
何か伝えたいとき、必要以上に喋らない子どもは、先生の目をしっかりと見て説明を聴けます。一方で、よく発言する子は疑問に思ったことをその場で質問したりします。
どちらが学力が上がりやすいかは別として、聴く態度としては静かに聴く子の評価が高くなります。
聴くときは静かに聴く。「聴くとき」と「発言するとき」は明確に区別を。
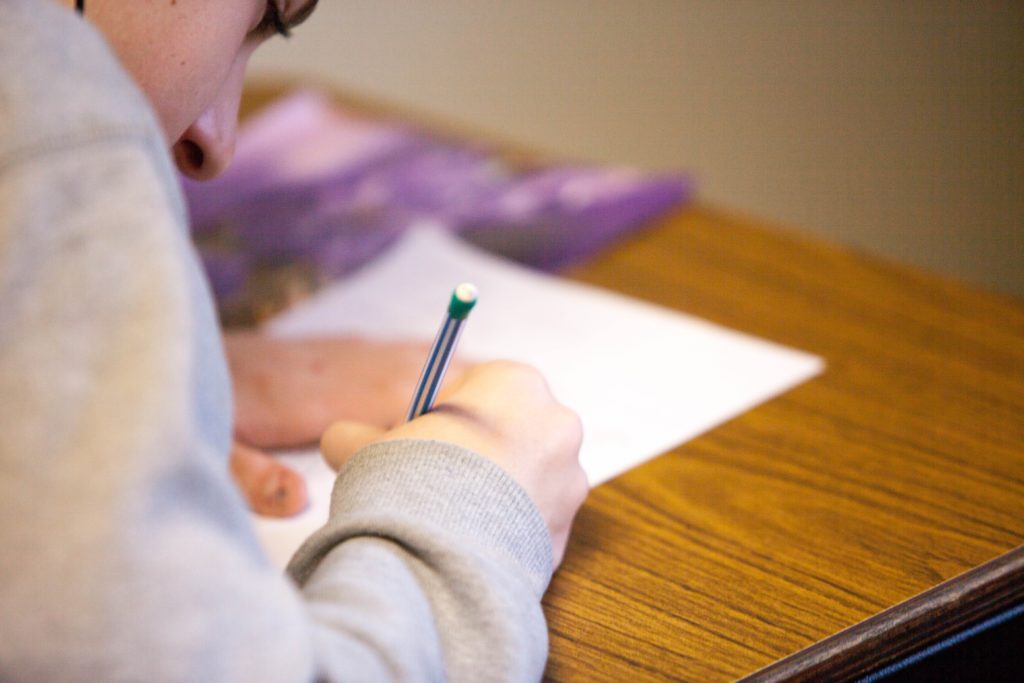
3.全体に意見を求められたときに発言する
”物静か”であることと矛盾しているように思えます。
授業内で、先生が全体に意見を求める場合があります。最近の教育現場では、先生から生徒に講義形式で”一方向的”に授業するのではなく、”双方向的”な授業展開をすることが多くなってきています。
授業に様々な手法の”アクティブラーニング”が取り入れられ、生徒が授業に積極的に参加することが求められています。
こういった参加型の授業で、どの生徒も消極的であると授業が成り立ちません。
そんな授業進行が行き詰ったときに、発言をすると、先生として非常に助かるのです。その発言を材料にして、授業が進展できるのです。発言が正しいか正しくないかは関係ありません。
全体が消極的なとき、授業に参加する生徒は先生としても助かる。
「この授業で先生が生徒に身につけてほしいことは何だろう?」と想像することで、授業の目的と合う発言ができるでしょう。
4.隣の人を静かに指摘できる
授業の形式で、グループ学習などをする場面があります。このような友達同士で勉強を教え合い、学び合う場合、ファシリテーターの役割が重要です。
※ファシリテーターとは 中立の立場でディスカッションなどを進行・促進する人 ここでいうと学校の先生のこと。
進行役になる先生が次の局面に移る時に指示を出します。
しかし、生徒の中には、けじめをつけられず、永遠と自分たちの話を続けてしまうことがあります。騒がしいと説明が行き届きません。
こんなとき、議論や話し合いを中断するように、”冷静に周囲を指摘できる”生徒は有用な人物と評価されます。
また、集中力にかける隣の友達に、そっと一言伝え、気持ちを授業に向けさせる。一瞬の出来事ですが、気配りをしてくれる生徒は先生としては貴重です。大人な生徒と言い換えてもいいでしょうか。
周囲が騒がしいときに、大声で「しぇーずぅーかぁーにぃーしぃてくださぁーい!」とここぞとばかりに前にでる子供もいますが、、、先生は「お前が一番うるさい」と心の中で思っているかも(-_-;)
指摘は全体ではなく、近くの人だけでいいのです。”静かさ”は自然と連鎖しますから。
冷静に、近くの友達をそっと授業に向けさせる。
メリハリがつけられる能力として評価されることは間違いありません。
5.提出物は必ず期限内にきちんと出す
当たり前の行動を当たり前にできる。これは優れた能力です。
先生からの連絡や指示に耳を傾けて、提出物を出し、適切な持ち物を持ってくる。これだけでも評価されます。
※学校の先生は大変 クラス全員の評価をするために、 授業の準備だけでなく、提出物のチェックなど 細かく管理しなければなりません。 しかも、担当するクラスは1つではなく、 他クラス、他学年もあり、大人数で大変です。
もし、期限内に提出しない生徒がいたらどうでしょう。チェックが出来ず、提出物を出すよう”催促する”仕事が増えてしまいます。
仕事が大幅に遅れてしまうのです。遅れた生徒の心証は決して良いものではないでしょう。
一方で、きちんと提出するだけでも、先生にとってはありがたい生徒です。
当たり前のことを当たり前のようにするだけでも、先生にとってはありがたい。

6.服装などで自己主張しない
- スカート丈
- シャツの乱れ
- 学ランの着方
- ボタンのとめかた
- 髪型
- 化粧・眉毛
- 香水
- 靴の履き方
など、容姿で主張が強い生徒は評価が高くなりません。
生徒指導は、非常に労力のいる仕事の1つです。人として守るべきルールを守るだけでも、先生の負担は軽減されますので、服装などを奇抜にしない方が賢明です。
校則に不満があるのも分かりますが、内申点という観点からすると反抗的なことは避けるべきです。
7.トラブルに関わらない
万が一、友人間のトラブル、一部の生徒の問題行動が起きた場合、関わらないことです。
先生の立場からすると、解決のために放置せずに事実確認をする必要があります。トラブルに関わる生徒全員から聞き取りなどをしなければなりません。
つまり、トラブルに関わる生徒が多ければ多いほど、全員から事情を聞く必要があり、時間も手間もかかってしまいます。
ですので、関わらない。ノートラブルが望ましいです。
※問題行動は入試に痛手 ”行動の記録等”として志望する高校に 提出しなければなりません。 特記事項として、問題行動の記録があれば 圧倒的に不利な状況です。 高校側も、高校生になってまで、 生徒指導をしたくありませんので。 高校でも問題を起こす恐れがあれば、 内申点、テストの得点に関わらず、 合格させる可能性は低くなるでしょう。
8.学ぶことを楽しんでいる
勉強を楽しむことです。これが最も大事かもしれません。
内申点を気にせず、目の前のことに夢中になる姿は応援したくなるものです。
高校に行くため、テストでいい点を取るため、他の人に認めてもらうため。そんな理屈は一切なしに、学ぶことを楽しむことがなによりです(*^^)v
では、今回は以上になります。
一般入試もそうですが、推薦入試を希望している人にとって、内申点は特に重要です。内申点をとっておいて無駄なことはありません。それでは(^^)/





コメント