
こんにちは、「学ぶことは真似ることから」まねこです。
効率重視の勉強をよく耳にします。
確かに、勉強において手っ取り早く成果を出せる方法があれば、迷わずその方法を選びます。
少し気になるのは、効率や合理性を追い求めすぎて、勉強そのものの探求が不足している子が多くなっていることです。
中学生にとって合理的・効率的より大事なこと【勉強の成果を上げる】
特に多くの中学生が、スマホを持ち始める時期でもあり、ネットから大量の情報に触れる機会が圧倒的に増えます。
当然、「定期テストで成績を上げる方法」「英語の勉強法」など検索することもあるでしょう。情報の中には、教育に関わるプロの意見や教育機関が発信する情報、成功者の知恵など有用なものも多くあります。
このページも勉強に励むすべての人に、少しでも参考になればと思い発信しています(._.)
成功者・経験者から合理性のある”効率的な勉強”は真似すべき
※合理性 論理にかなっている。目的にあって無駄がない。 ※効率的 労力に対するはかどり具合。仕事の能率。
「勉強のやり方」の”正解”を探し回ることは悪いことではないです。自分で調べたり、試行錯誤したり。積極的にいろいろ試して効果的な勉強を探る。
とはいえ、注意が必要です。「勉強のやり方」の”正解”を探し回ることばかりやっていませんか。
スマホだけでなく、パソコンやタブレットなどを持つ中学生は、情報収集ができる反面、情報収集に振り回される子がいます。
「やれあれがいい、これがいい。これはダメ、あれもダメ。」となりがちで、情報収集に時間を割いて、勉強する時間を削っている。
ここで伝えたいことは、中学生にとって合理的・効率的な勉強よりも、遥かに効果的なことがあるということです。
合理的・効率的より、夢中になることが遥かに大事。
はっきり言って、”夢中”にさえなれば、不合理であれ、非効率であれ、関係ありません。
中学生にとって、学習効果が最もあるのは、正解の「勉強のやり方」で学ぶことではなく、夢中になること。手段や方法は二の次でOKです。

合理性とか効率性とはどうでも良い?
『”夢中”にさえなれば、不合理であれ、非効率であれ、関係ありません。』 と伝えた理由は2つあります。
おそらく、この文章を読んでいる多くの人は、中学生あるは中学生を子に持つ親、中学生の教育に関わる方だと推測しています。
中学生の勉強は、「初等中等教育」であり、大学などの「高等教育」の前段階です。
初等中等教育の役割(読み飛ばしても構いません(^▽^;))
高等学校段階までの初等中等教育は、人間として、また、家族の一員、社会の一員として、更には国民として共通に身に付けるべき基礎・基本を習得した上で、生徒が各自の興味・関心、能力・適性、進路等に応じて選択した分野の基礎的能力を習得し、その後の学習や職業・社会生活の基盤を形成することを役割としている。
基礎・基本を学ぶわけですから、中学段階で高度なことはありません。乱暴な言い方ですが「やれば出来る」レベルです。
つまり、基礎・基本の習得に、手段・方法による”違い”はあまりないのです。夢中になれば、勉強のやり方が悪く、多少効率が悪くてもすぐに追いつけます。
理にかなっている勉強方法は、すぐには分かりません。勉強していくうちに、気づいていくことが多いのです。
特に中学生の中には、勉強することに慣れていない子も多く、「勉強って何するの?」という初歩的なことさえ分からない子もいます。
先生、親、塾の講師、先輩、友人などを真似して、勉強の”型”を学び、”型”を真似ることから始めるのです。その勉強の”型”の理由や合理性などは後回しで構いません。
勉強に慣れてから、自分の頭で考え工夫をして、アレンジしていくことで、効率が身につきます。

中学生が夢中になるきっかけは?
中学生のとって、勉強に夢中になれるときは、どんなときでしょうか。4つ紹介します。
1.時間を制約されたとき
- 制限時間を設ける
- 試験に申し込む
勉強中であれば、キッチンタイマーなどで、細かく時間制限をして勉強することです。自然と没頭できます。
また、受験直前はどの生徒も無我夢中で勉強します。今まで鉛筆も持ったことがないような子も、積極的に質問をするなど、解決しようと必死になります。
試験直前は高い集中力を発揮しますので、極端なことを言うと、試験に申し込めば良いのです。英検などの試験とか。
勉強せざるを得ない状況をつくることも、夢中になるきっかけになります。
2.危機感を感じたとき
- 定期テストの成績の低下・低迷
- 模擬試験の判定
中学生にとって、学校の定期テストへの関心は非常に高いです。友達との差も知れるため、誰が成績何番とか、誰より頭が悪いとか、前より点数が上がったとか。定期テストに無関心な子はいません。
そして、その定期テストで成績が低迷し危機感を感じたときは、夢中になって勉強するきっかけになることがあります。
また、模擬試験では、志望校の合格判定の基準として、A~Eで判定されるテストがあります。
自分の将来の判定がアルファベットや数字で示され、危機感を覚え、必死になって勉強することも多く見られます。
危機感を感じたときは夢中になれるチャンス
特に、親と学校、親と学習塾、などで三者面談をきっかけに変わる子が多くいます
時間をとって、具体的な数値を確認しながら、将来について話し合うことが、夢中になって勉強するきっかけになるでしょう。
3.結果が出たとき
- テストで優秀な生徒を上回った
- テストで席次が大幅に上がった
「意外と自分は出来るんだ」とちょっとした成功体験をすることで、後に夢中になって勉強し始めることがあります。
勉強に対して自信を持つことで、夢中になれます。少しだけ上の目標設定をして、超えていくことが自信につながります。
4.夢・目標が明確になったとき
- 将来やりたいことが明らかになった
- 達成したいことがある
将来就きたい職業がある、行きたい学校がある、やりたいことがある。など、勉強の目的が明確になったとき、夢中になって勉強できます。
「”好きなこと”はこれっ」とはっきり言えるようであれば、”好きなこと”と勉強をつなげることで、モチベーションは高まります。学んでいることは、いずれ好きなことに関わってきます。

夢中になるには、まずこれだけやればいい3選
勉強になかなか没頭できない場合は、勉強することを絞りましょう。やることを1点に絞った方が夢中になれます。
上記3つのうちどれか1つを徹底的にやりこみましょう(^O^)/
1つでも夢中になってやり込めば、自ずと能力は引き上がります。これだけは絶対誰にも負けないことを持つことで、自信がつきます。
まずは、自分の武器を1つを持ちましょう。
また1つを高めれば、上達する勉強のやり方を経験できます。その経験は他の科目の勉強に応用できるので、他の科目も同様に勉強すれば、全科目の成績は上がっていきます。
義務感を感じながら勉強しても、効果は薄く、コツコツやっても身になりません。好きなこと、得意なこと、人に勝てることに絞って夢中で勉強べきです。
夢中でない人がコツコツやっても、夢中の人には絶対勝てない。
勉強のやり方でいくら遠回りしようが、非効率だろうが、不合理であろうが、夢中であればすぐに改善できます。”夢中”が最強( `ー´)ノ
では、今回は以上になります。
夢中になるきっかけを待つのではなく、自分で作っていきましょう!それでは(^^)/
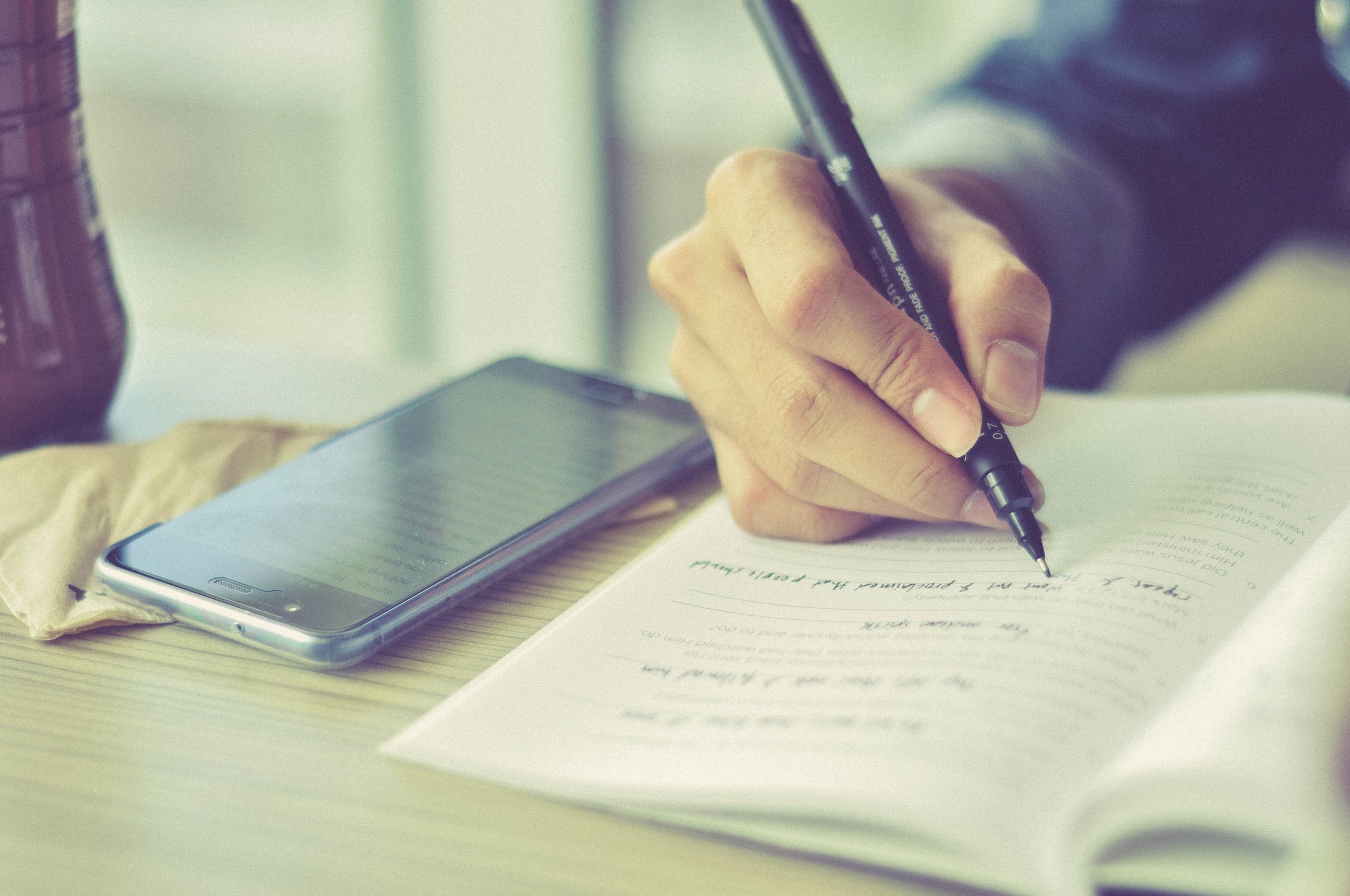




コメント